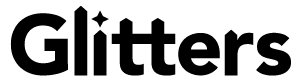戦いを終えて最後の“祭り"を楽しむデフアスリートたち
コミュニケーションの壁を乗り越え、大会を成功へ

「大会の成功に満足している」と東京大会を高く評価したアダム・コーサ会長
閉会式を前にデフリンピックスクエアでは記者会見が行われ、冒頭のあいさつで国際ろう者スポーツ委員会のアダム・コーサ会長は、こう評価した。また東京デフリンピック運営委員会・久松三二委員長も「今大会は大成功だった。100周年にふさわしい大会になったと満足している。その裏には大会を盛り上げてくれた日本選手団や各国の選手たちの活躍があり、そして観客の方々、国民にも応援をいただき、大会を支えてもらった」と述べ、大会成功の喜びとともに感謝の言葉を述べた。
聴覚障がい者の国際大会であるデフリンピックを日本で開催したのは今回が初めてだった。そのため、運営においてはコミュニケーションツールなど、さまざまな課題があった。しかし、その課題解決に取り組んだことによって大きな成果が生まれた、と久松委員長は語る。
「今大会は、当事者の団体である全日本ろうあ連盟と、行政をはじめとした聴者の皆さんとどのようにコミュニケーションをして運営していくかが、大きな課題の一つとしてあり、現場ではさまざまな壁がありました。そのようななかでもお互いにコミュニケーションを円滑に築き上げることができたことが、大会の成功に結び付いたと思います。そして大会を通して、さまざまな国の競技団体と連携し、パイプを作ることができました。こうした初めての試みが数多くありました。まだ十分に期待に応えることができなかったことも多かったと思うが、情報保障を確立させ、共生社会を築き上げていくための大きな第一歩が踏めたのではないかと思います」
東京都スポーツ文化事業団・デフリンピック準備運営本部の北島隆最高執行責任者(COO)も「今大会の大きな目的は、コミュニケーションの壁を超えるということだったが、大人も子どもも、外国の方も、選手も観客も、耳のきこえにくい方も、ほかの障がいがある方も、みんなが一つの場所で応援し、楽しむといった、共生社会の縮図を今大会を通じて作れたと思う。すべての関係者の皆さまのおかげで感謝したい」と語った。
今大会を契機にあらゆる可能性に挑戦できる社会へ

史上最多のメダルを獲得した日本選手団。会場を訪れた観客に感動を与えた
「今大会を成功させるために、東京を除くすべての道府県にプロモーションのために車で回り、行政や役所にも協力をいただいて、その地域にゆかりのある選手や出身の選手の体験会やイベント、講演会を付随していただきました。そのおかげで、各自治体で応援するということが起こり、行政やマスコミの多大なる尽力もあってたくさんの宣伝活動ができました」
そして東京デフリンピック開催を機に、期待が寄せられているのが、共生社会実現に向けた社会における聴覚障がい者の立ち位置の変化だ。久松委員長はこう語る。
「今大会ではあらゆる可能性にチャレンジすることができました。国内においてもあらゆる機会をつくり、さまざまな挑戦ができ、各所でチャレンジする気持ちを持つことができたと思います。スポーツ基本法にも初めて“デフリンピック"という言葉が入りました。選手、スタッフ、団体、関係者の方々がさまざまな可能性に自信をもってチャレンジできる、今大会はそのスタートになったと思っています。当事者が自分で意見を述べ、要求をし、企画をしていく、そんな社会を構築していく契機になったと思いますし、チャレンジの幅が広がったと思っています」

旗手の大役を務め、スタンドに笑顔を向けるバスケットボール女子・若松優津(左)とサッカー男子・松元卓巳(右)
26日の夕方には、東京体育館で閉会式が行われ、東京都の小池百合子知事や、大会期間中には空手などを観戦された秋篠宮家の次女・佳子さまも出席。史上初の金メダルに輝いたバスケットボール女子の若松優津と、銀メダルを獲得したサッカー男子の松元卓巳の両キャプテンが旗手を務めた。
閉会式の最後には、フランス語の「bon(良い)」と日本文化の「盆」をかけ、「良い未来」という意味が込められた、アーティスティックプログラムの「ボンミライ!(Bon Mirai!)」が行われた。2カ所に設置された“やぐら"に色とりどりの衣装をまとったパフォーマーたちが登場すると、各国の選手たちも一緒になって盆踊りを楽しみ、12日間にわたって行われた熱戦のフィナーレを飾った。
(文・斎藤寿子/写真・竹内圭)
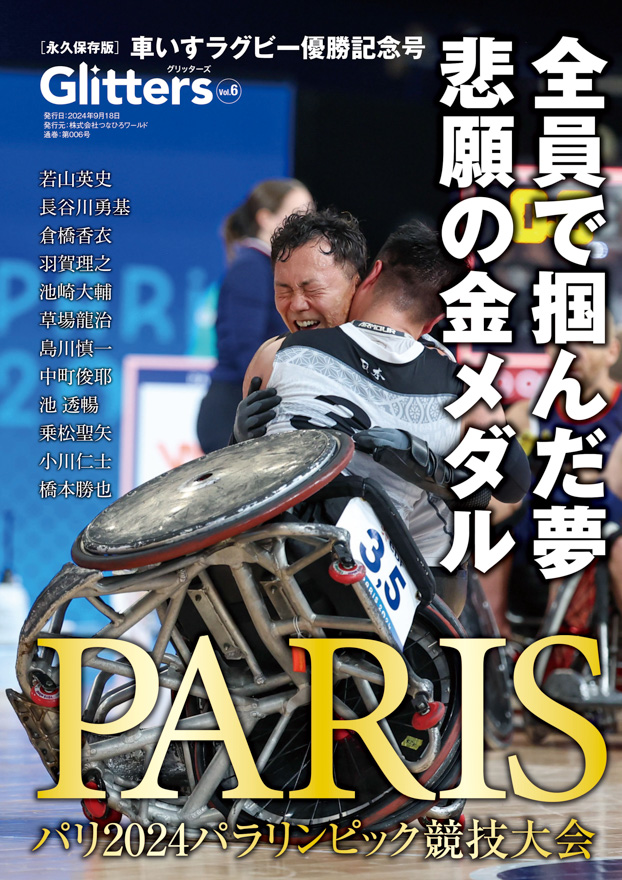
最新号
購入する
RANKING
- 1
2025 IWBFアジアオセアニアチャンピオンシップス
車いすバスケ女子日本代表、2大会連続で世界選手権出場が決定!勝利の裏にあった予選リーグからの伏線
- 2
2025 IWBFアジアオセアニアチャンピオンシップス
車いすバスケ男子日本代表、オーストラリアとの激闘で示した現在地
- 3
2025 IWBFアジアオセアニアチャンピオンシップス
車いすバスケ男子日本代表、強敵イランを撃破!前回大会の雪辱を果たし、世界への切符を獲得!
- 4
東京2025デフリンピック
28万人が観戦し熱狂!日本選手団は史上最多の51個のメダルを獲得!共生社会実現の第一歩に
- 5
第36回日本パラ陸上競技選手権大会【2日目】
若い世代へ兄弟へ 受け継がれる陸上への情熱~「第36回日本パラ陸上競技選手権大会」(2日目)~