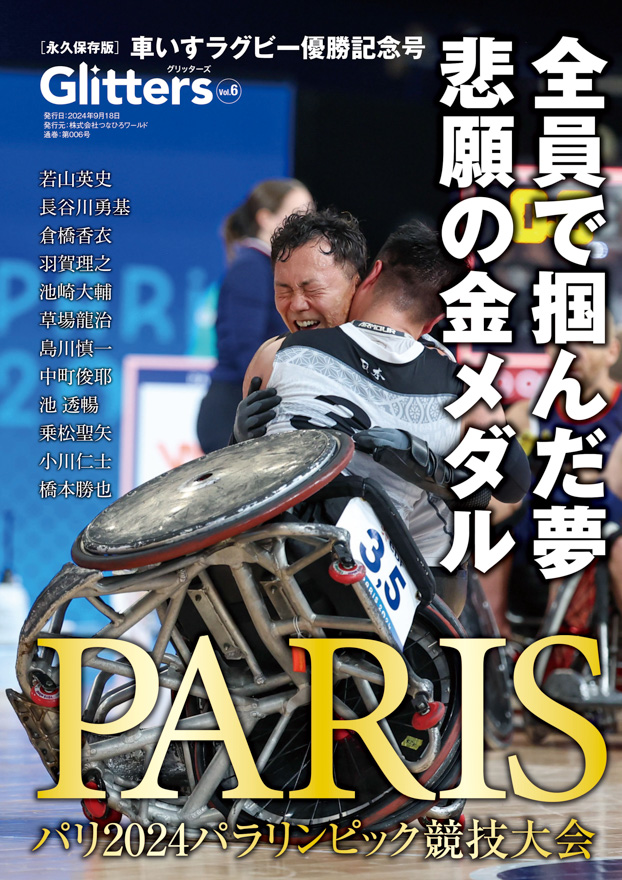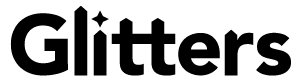爆発力で試合を動かし、勝負どころで打ち切る。得点源としてチームを勝利へ導いた北田千尋
チームを救ったベテラン勢のシュート力
僅差による勝利だったが、これは偶然の産物ではなく、用意周到な準備の賜物だった。実は、世界選手権の出場権がかかった大一番の準決勝に向けて、女子日本代表は予選リーグから伏線をはっていたのだ。今大会、ディビジョン1の日本、中国、オーストラリアの3カ国は予選リーグでは2試合ずつ総当たりで対戦。そのため、日本とオーストラリアはすでに2度、試合を行っていた。そして、最も大事な準決勝でオーストラリアと当たった場合を想定し、日本はその2試合いずれにも大一番に向けて布石を投じていた。それは全員でプレータイムをシェアし、常にフレッシュな状態でプレーすること。そうして固定した少ないメンバーで戦うオーストラリアをできるだけ疲弊させた状態で、準決勝を迎えるという策だった。準決勝でも、3Qまで目まぐるしいほどの選手交代をした背景には、そうした一貫した狙いがあったのだ。日本はどの選手が出ても、ボールマンへのプレッシャーを徹底したディフェンスで、失点を抑えるとともに、オーストラリアを体力的にも精神的にも消耗させていった。
ただ、日本も得点が伸び悩み、我慢の時間が多かった。そんななか、得点力でチームをけん引したのが何度も世界の舞台を経験してきたベテラン勢だ。1Q、網本麻里(4.5)がドライブで切り込みレイアップシュートでチーム最初の得点を挙げると、中盤にはキャプテン萩野真世(1.5)が3ポイントシュートを炸裂。萩野は1Q終盤、さらには2Q序盤にも得点を挙げ、前半はFG成功率75%を誇った。

落ち着きと確率の高さで前半を支えた萩野真世
「パリでの選手村では“またみんなで頑張ろう!"と思っていたのですが、帰国して日常生活に戻った時に“あと4年、自分は本当にこの生活を続けられるのか"という気持ちが出てきた。そう思ったら体育館やジムに行こうと思っても靴を履くこともできず、外に出られないという日々が続きました。結局クラブチームの活動も休んで1カ月、何もしない時期を作ったんです。そしたら、自然と“バスケットがしたいな"と思えた。“まだまだうまくなれるし、まだまだバスケットを楽しめる"と思えたのでロスを目指すことにしました」
そして、今、北田には新たな目標があり、それを叶えるために日々、努力している。それが今大会の好調の要因でもあった。
「パリのドイツ戦で3ポイントを8分の4で決めて、13点差から一時は逆転することができたんです。その時に3ポイントの威力ってすごいなと。そして自分が何かで世界一になれるとしたらこれしかない、と思いました。だから個人の目標として“世界一の3ポイントシューター"を掲げ、練習にも力を入れてきました。それが今大会はいい方向にいっているのかなと思います」
明暗を分けた予選リーグから積み重ねてきた疲労度の違い
そんな北田の活躍で、日本は28-25となんとかリードを保ったまま、試合を折り返した。しかし続く3Q、オーストラリアに13得点を奪われて逆転を許した。さらに4Qの前半、日本は立て続けにオーストラリアのミスを誘う好守備を見せるも、得点につなげることはできず、約7分間、無得点。一方、オーストラリアは中盤に連続得点し、流れを引き寄せつつあった。それでも日本には「ディフェンスさえしっかりとやれば、必ず勝機はある」という自信があった。予選リーグから40分間、強度の高いディフェンスをしてきた成果が如実に表れ、4Qには2人の主力が5ファウルで退場するほど、オーストラリアは目に見えて疲弊していたからだ。

6得点・13リバウンド・7アシストとオールラウンドに貢献した網本麻里
翻ってオーストラリアはやはり疲労困憊だったのだろう。フリースローに加えて、最後はオフェンスリバウンドを取り、3度あったペイントエリアからのシュートチャンスを落とした。
44-42。わずか2点差での辛勝だったが、しっかりと大一番に向けて準備してきた日本の戦略的勝利だった。
大会最終日の15日には、決勝で中国と対戦する。予選リーグの初戦は51-44と日本が勝利を収めたが、2試合目は25-56と完敗。果たして3度目は、どんな結果が待ち受けているのか。「パラリンピックのメダルチームに、今の日本のバスケがどれだけ通用するのか。自分たちの現在地を知ることのできる絶好のチャンスなので、勝利を目指すと同時に思い切ってチャレンジしたいと思います」と添田智恵ヘッドコーチ。元安陽一アソシエイトヘッドコーチと二人三脚で作り上げてきたチームには、今、一体感がある。共通した認識を持った結束力を武器に、女子日本代表は全員で優勝を目指す。
(文・斎藤寿子/撮影・竹内圭)
【車いすバスケットボール】
一般のバスケットボールとほぼ同じルールで行われる。ただし「ダブルドリブル」はなく、2プッシュ(車いすを漕ぐこと)につき1回ドリブルをすればOK。
選手には障がいの程度に応じて持ち点があり、障がいが重い方から1.0~4.5までの8クラスに分けられている。コート上の5人の持ち点の合計は14点以内に編成しなければならない。主に1.0、1.5、2.0の選手を「ローポインター」、2.5、3.0、3.5を「ミドルポインター」、4.0、4.5を「ハイポインター」と呼ぶ。
コートの広さやゴールの高さ、3Pやフリースローの距離は一般のバスケと同じ。障がいが軽いハイポインターでも車いすのシートから臀部を離すことは許されず、座ったままの状態で一般のバスケと同じ高さ・距離でシュートを決めるのは至難の業だ。また、車いすを漕ぎながら、ドリブルをすることも容易ではなく、選手たちは日々のトレーニングによって高度な技術を習得している。
ジャンプはないが、ハイポインターが車いすの片輪を上げて高さを出す「ティルティング」という技がある。ゴール下の激しい攻防戦の中、ティルティングでシュートをねじ込むシーンは車いすバスケならではの見どころの一つだ。
一般のバスケットボールとほぼ同じルールで行われる。ただし「ダブルドリブル」はなく、2プッシュ(車いすを漕ぐこと)につき1回ドリブルをすればOK。
選手には障がいの程度に応じて持ち点があり、障がいが重い方から1.0~4.5までの8クラスに分けられている。コート上の5人の持ち点の合計は14点以内に編成しなければならない。主に1.0、1.5、2.0の選手を「ローポインター」、2.5、3.0、3.5を「ミドルポインター」、4.0、4.5を「ハイポインター」と呼ぶ。
コートの広さやゴールの高さ、3Pやフリースローの距離は一般のバスケと同じ。障がいが軽いハイポインターでも車いすのシートから臀部を離すことは許されず、座ったままの状態で一般のバスケと同じ高さ・距離でシュートを決めるのは至難の業だ。また、車いすを漕ぎながら、ドリブルをすることも容易ではなく、選手たちは日々のトレーニングによって高度な技術を習得している。
ジャンプはないが、ハイポインターが車いすの片輪を上げて高さを出す「ティルティング」という技がある。ゴール下の激しい攻防戦の中、ティルティングでシュートをねじ込むシーンは車いすバスケならではの見どころの一つだ。